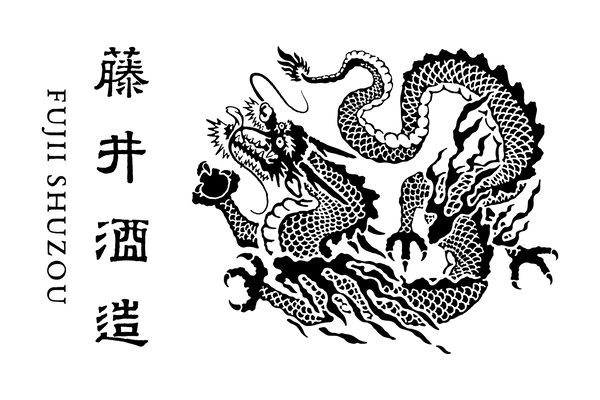静けさと深みの一杯を。
私たちの酒造りは、制御ではなく共生です。
自然のゆらぎを受け止めながら、その中で輪郭を整える。
人の役割は管理ではなく調律。微生物の働きを妨げないよう、
原料・温度・時間の調和を見極めていきます。
これを、私たちは「余白ある酒造り」と呼んでいます。
三つの基軸
この「余白ある酒造り」を実現するために、私たちは三つの基軸を日々の基準としています。
-
自然発酵
蔵に棲む天然の蔵付き酵母で仕込みます。乳酸菌も添加せず、自然の力が立ち上がるのを待つ。
これは、効率を犠牲にする選択です。でも、この"非効率"の中にこそ、複雑で奥行きのある味わいが生まれます。
人為的な介入は最小限に留め、微生物の自然な均衡を尊重する。それが、私たちの基本姿勢です。
-
生酛の骨格
時間をかけて育てる生酛は、日本酒造りの古典的手法です。乳酸菌が自然に増殖するのを待ち、酵母がゆっくりと立ち上がる。
この時間が、太すぎず細すぎない輪郭を形成します。香味がゆっくり広がる余白を残し、飲むほどに芯が見えてくる佇まい。それが、生酛ならではの魅力です。
-
温度設計
温度は、発酵という生命現象を調律する最も繊細な要素です。仕込み・発酵・貯蔵の各段階で温度を丁寧に見極め、香りと旨みの重なりを整えていきます。
ただし、"完璧にコントロールする"わけではありません。自然のゆらぎを受け入れながら、その中で対話する感覚です。

酒は、蔵の可視化である
一本の酒は、どのように生まれるのか。
私たちは「蔵という場が、時間とともに表れたもの」だと考えています。
酒 = 可視化 { 蔵 × 時間 }
そして、蔵 = 場 × 菌 × 手
場:木造蔵の構造、温湿度のリズム、蔵付き微生物叢、花崗岩軟水、微気候
菌:蔵付き酵母・乳酸菌の移り変わり、共存のバランス
手:洗米・浸漬、麹づくり、酒母、もろみ管理、上槽といった造り手の技
時間:発酵日数、熟成、瓶内での変化
その年、その蔵、そのときだけの表情。
それが、生きた酒の証です。

変えないために、変える
伝統を守るとは、何も変えずに残すことではありません。
藤井酒造が目指すのは「古くて新しい」酒造り。過去の知恵に学びつつ、必要な部分を更新していく。「変えないために、変える」。そんな姿勢で、観察と手仕事を重ねています。
自然発酵の酒造りには予測できないことも多く、失敗もあれば発見もあります。その積み重ねが、次の一滴につながります。この揺らぎの中にこそ、酒の生きた魅力があると考えています。

蔵の記憶を、未来へ
地域の水と空気、そして受け継がれてきた手の記憶が重なる「場」を、次の世代へ渡していくこと。
1907年に灯った火を、今の蔵でつなぎ、これからへと引き継いでいくこと。
完璧ではない。けれど、試し、学び、前へ進み続ける限り、蔵の記憶は途切れないと信じています。